
学会の活動
研究会報告
ここでは、研究事例・交流部会、研究会(学会助成研究)での活動についてご紹介します。
次回開催予定 Next Event
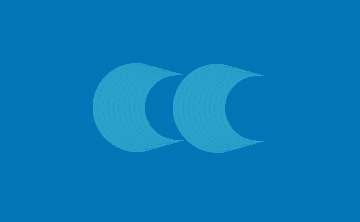
定例活動報告
情報流通構造の事例研究会(12月23日)実施レポート
12月23日に開催された情報流通構造の事例研究会では、
これまで継続してきた「検索エンジン」「SNSアルゴリズム」「デジタル情報流通構造」に関する議論を総括し、
アルゴリズムと人間の認知・感情・行動が結合した現代的な情報流通の特性について整理を行った。
冒頭では、デジタル化によって情報量は飛躍的に増大した一方で、
「同じ情報を同時に共有する公共空間」が希薄化している現状が確認された。
新聞の一面やテレビの全国中継といった共通体験を前提とした情報環境から、
個別最適化された情報提示へと移行した結果、同一の事象であっても、
受け手によって見える情報や文脈が大きく異なる構造が生まれている。
議論では、情報流通を「一次情報(企業発表・オウンドメディア)」「二次情報(取材・記事化・ニュース転載)」
「三次情報(SNSでの拡散・引用・再解釈)」というレイヤー構造で捉え直した。
そのうえで、炎上事象などに見られるように、切り取られた断片情報が感情と結びつき、
瞬時に拡散・再編集される過程が、世論形成に大きな影響を与えている点が共有された。
参加者からは、「アルゴリズムは万能ではなく、リアルな人間関係や生活文脈には及ばない」
「情報の拡散には数理的評価だけでなく、心証や感情が強く作用する」「デジタル群集心理が特定の方向に働くことで、
拡散が加速・偏在する」といった指摘があった。
アルゴリズムは人を直接支配する装置ではなく、
人間の認知バイアスや感情と結合することで影響力を持つ点が確認された。
また、フィルターバブルとエコーチャンバーの違いについても整理が行われた。
前者が情報への接触範囲の縮小を指すのに対し、
後者は反応が返ってくる環境そのものが自己強化的に循環する構造であり、
人為的に設計された装置というよりもエコシステムとして理解すべきであるとの認識が共有された。
本研究会では、公共空間が消失したのではなく、
分散・断片化した形で存在しているという視点を提示した。
異なるトライブが完全に交わらないのではなく、
生活文脈や役割共有といった限定的な接点において重なり合う領域が、
現代的な公共空間として機能している可能性が示された。
本定例会をもって、当研究会における一連のアルゴリズム・情報流通構造研究は一区切りとし、
今後は新たな事例や変化を踏まえた議論へと接続していく予定である。
以上
(田代順)
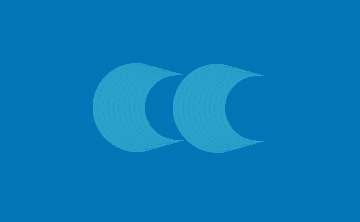
30周年記念事業「経営者インタビュー調査」進捗報告
「経営者インタビュー」調査で得られた20社、約40万字のテキストデータをもとに、
M-GTAの手法にて定性分析を進めています。
「広報研究」へ投稿される論文作成と3月のシンポジウムでの発表を目指し、
27名の公募メンバーとともに議論を進めています。
ご期待ください!
シンポジウムについては改めて参加募集いたしますが、概要を先行してお知らせしておきます。
詳細は少し変更になる可能性がありますのでご留意ください。
日時:3月17日(火)17:30~20:00
シンポジウム会場:上智大学の大教室(2号館3階の予定)
懇親会会場:同学生食堂
参加費:無料(吉田秀雄記念事業財団からの助成金を活用予定)
(柴山慎一 30周年記念事業プロジェクトマネジャー)
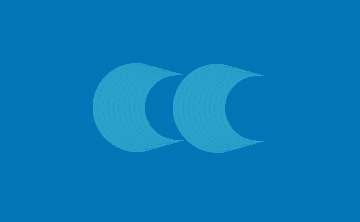
情報流通構造の事例研究会
12月23日の研究会では、これまで取り組んできた「アルゴリズム三部作」の総括として、
生成AIが情報流通にもたらしている最新の構造変化をテーマに扱います。
ChatGPT、Google SGE、PerplexityなどのAI検索統合を前提に、
情報の発見・評価・拡散の構造がどのように変わりつつあるのかを整理し、
PR実務における応用、E-E-A-T、危機管理、SNS波形設計までを体系的に解説します。
広報実務者、研究者のいずれの立場にとっても、
今後の議論や実務設計の基盤となる内容です。
関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
参加をご希望の方にはGoogleカレンダーで招待します。
■準備の都合上、前日までに参加希望の旨をお知らせください。
■オンライン開催 12月23日17時~18時
■本研究会の到達目標
• 生成AIが情報流通に加えた「第四のレイヤー」を理解する
• 検索・SNS・危機管理におけるPR実務への応用を体系化する
• リスクと倫理を整理し、研究と実務の橋渡しを行う
■参加申し込みは:田代 順tashiro@materialpr.jpまで
(田代 順)
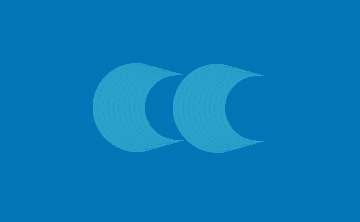
関西部会・研究会報告
関西部会では広報研究の活性化に資するべく研究会を定期的に開催しています。
2025年度の第1回研究会は、2025年10月18日(土)に、
「広報のクリエイティブ」をテーマに開催いたしました。この研究会は、
日本広告学会関西部会との合同研究会として実施し、
両学会あわせて26名が参加する盛況となりました。
メインゲストにPR会社マテリアルの新進気鋭のクリエイターである常谷友梨絵様をお招きし、
PR会社のクリエイターはどのようなことを考えながら活動しているのかについてお話を伺った上で、
パネルディスカッションで広告のクリエイティブと比較しながら議論を深めました。
第2回研究会は、2025年12月11日(木)に、
「宝ホールディングス歴史記念館見学会」として開催いたしました。
参加者15名が普段は一般非公開の記念館に特別に入館し、
平尾嘉之館長による展示内容の説明を受けながら館内を巡りました。
また、その後の意見交換では、
社員を対象とした企業博物館の運営に関して活発な議論が展開されました。
なお、今回の研究会には、在関西の複数の企業博物館の関係者にも参加いただけたことで、
濃密な議論が実現しました。終了後は近隣のお店で忘年懇親会を開催し、
会員相互の交流を深めることもできました。
第3回研究会は2026年2月に開催予定です。
詳細が固まりましたらあらためて会員のみなさまにご案内差し上げます。
(伊吹 勇亮・関西部会長)
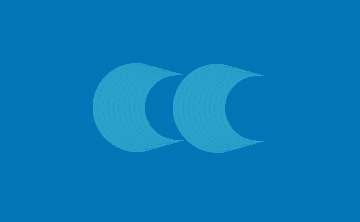
SNS選挙研究会活動報告
<第6回研究会開催>
実施日:11月10日(火)18時~20時オンラインにて実施
参加者:喜多村、ブレッドスミス、波、北島、石川
〇広報学会大会での発表振り返り
【ポスター発表2件】
ブレッドスミス美奈子
「YouTube上の党首討論コンテンツに対するコメント分析による視聴者の政治的関心の可視化」
喜多村祐介「2025年参議院選挙において躍進した政党のYouTubeコメント分析」
「人物評価が52%、政策評価40%であるとわかり興味深かった」
「政策評価の細分化についてはできそう」「学会ではAI使った分析に関心が高かった」
「保守とリベラルを区別すればいいのか」といった議論がなされた。
【口頭発表】
石川慶子「選挙におけるSNSの有効性と課題を広報視点から考えるー2025年参議院選挙から」
・議席を伸ばした政党のSNS,AI活用共通要素が判明した
・学会発表でPR会社の介入が確認できた。
・デマ情報拡散防止への関心が多く見られた
・政党ではなく個人でSNS戦略を成功させている事例を次は分析したい
そのほか
・日本テレビ政党公式記者会見ランキングでは、
YouTube視聴回数10月のトップは意外にも榛葉幹事長。高市さんを抜いていた。
この要素について議論し、要素が分解できないか討議。
・ニューヨーク市長マムダニ氏のSNS戦略:完成度の高いプロによる動画制作でステージが変わったのではないか。
〇ヒヤリング候補者には討議
〇次回の研究会開催:12月22日(月)18時
(主査:石川慶子)
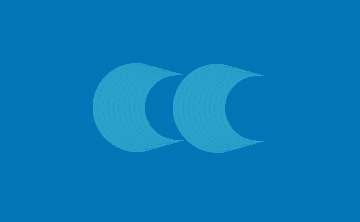
30周年記念事業「経営者インタビュー調査」進捗報告
30周年記念事業のクロージングに向けて、「経営者インタビュー調査」の結果分析を進めています。
昨年の全上場企業向けアンケートで「インタビュー対応可」と回答のあった
45社にインタビュー申込を行い、この8月~11月の間に20社のインタビューが実施できました。
20社は東京や大阪の大企業はもちろんのこと、地方企業や中堅規模の企業も含まれており、
良好なサンプルになりました。
3月のシンポジウムと次号の「広報研究」で結果を公表する予定ですので、ご期待ください。
(柴山慎一・30周年記念事業プロジェクトマネジャー)
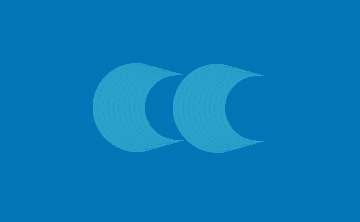
サステナビリティ広報戦略研究会の第3回研究部会の開催報告
サステナビリティ広報戦略研究会の第3回研究部会を
2025年11月28日(金)19:00~、新宿・損保ジャパン本社ビルとZOOMのハイブリッドで開催しました。
株式会社 良品計画広報・ESG推進部 部長の阿南 理恵氏をお迎えして
「創業から変わらない無印良品の思想と、変わるコミュニケーション」を
テーマにご講演いただいた後、40分程度、
部会員等も交えてサステナビリティ広報のあり方や円滑な推進方法についての討議をしました。
会合には、主査チーム(安部、加藤、本田、永田、折笠、駒橋、柴山、杖村、竹内)含み
30人が出席し、有志で講師を交えての懇親会も開催しました。
次回の第4回会合は、2026年1月30日(金)19時~、
部会員である安藤光展氏(法政大学 客員研究員、サステナビリティコミュニケーション協会代表)に
「サステナビリティの社内浸透とその実装」をテーマに講演をいただき、
メンバーで討議します。
(安部由紀子)
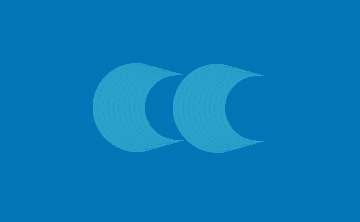
理論研究部会2024:定例会7・8月報告、次回予告
本部会では毎月海外の広報研究資料を読み、議論をしています。
【報告】第15回 7月19日(土) 報告者:村上信子(大分県立芸術文化短期大学)
テーマ:国際報道における国益フレームが世論に与える影響
論文:Brewer, P. R. (2006).
National Interest Frames and Public Opinion about World Affairs.
Harvard International Journal of Press/Politics, 11(4), 89–102.
https://doi.org/10.1177/1081180X06293725
第16回 8月15日(土) 報告者:安部由紀子(北九州市立大学)
テーマ:ゼレンスキー大統領の動画分析
論文:Lim, T. H., Yang, S. C., Ng, K. T., Quek, S., & Pang, A. (2025).
Seizing the narrative in a global information war:
Examining president Volodymyr Zelenskyy’s media communication strategy.
Journal of Communication Management, ahead-of-print(ahead-of-print).
https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2024-0182
【予告】第17回 報告者:古橋正成(オズマピーアール)
テーマ:環境プログラムにおける倫理的正統性とPR
論文:Hurst, B., Johnston, K. A., & Messner, R. (2025).
Signaling cognitive and moral legitimacy by a voluntary environmental program:
Navigating the diffusion-impact paradox.
Public Relations Review, 51(4), 102593.
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2025.102593
開催日程、内容:https://bit.ly/rkbhi
参加希望者の連絡先:国枝( t_kunieda@sophia.ac.jp )
(国枝智樹)
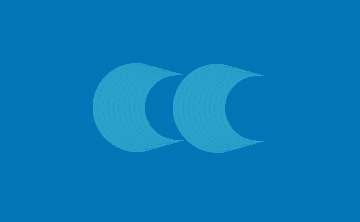
アルゴリズム研究「情報流通構造の事例研究会」
6月以降、定例開催が途絶えておりましたことをお詫び申し上げます。
情報流通構造の事例研究会「アルゴリズム研究」を9月より再開いたします。
次回は 9月17日(火)17:00~18:00、オンライン開催 です。
前回(6月18日)は「検索エンジンとアルゴリズムの進化と広報対応」をテーマに、
検索技術の歴史や広報における“発見設計”の重要性について議論しました。
今回はテーマを進め、「現在のデジタル空間における情報・ニュースの拡散の仕組み」 を読み解きます。
SNS、とくにX(旧Twitter)のトレンド形成やニュースプラットフォームでの転載ルールなど、
デジタルPRの構造を多層的に捉え、大きな論調をいかに設計できるかを議論したいと考えています。
資料は事前に共有いたします(前回レポート、完成前の参考資料含む)。ぜひご参加ください。
参加受付:tashiro@materialpr.jpまで
(田代)
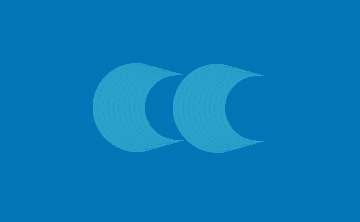
30周年記念事業の進捗報告
1.広報学会30年史は最終稿の確認をしています。
9月末の発刊目指して最終コーナーを回りました。
皆様のお手元には10月には届く予定です。完成をお楽しみに!
2.「経営機能としての広報」についての経営者インタビューが進んでいます。
昨年のアンケートで「インタビュー受諾可」としていた45社に申込をし、
その中から、この8、9月にインタビューを受けてくれる企業の経営者にインタビューを始めています。
インタビューへの参加希望者27名にも同席して頂きながら、貴重なインプットができています。
10月12日の東京都市大での研究発表全国大会で速報の発表をしますので、こちらもご期待下さい。
(柴山慎一・30周年記念事業TFプロジェクトマネジャー)
過去の研究会報告


設立30周年記念事業の進捗報告

第31回研究発表全国大会にて3名が発表

定例活動報告と次回開催

理論研究部会2024:第17回予告

サステナビリティ広報戦略研究会・第2回会合の開催報告

30周年記念事業の進捗報告

SNS選挙研究会活動報告

第98回広報塾開催のご案内

第97回広報塾開催告知

第96回広報塾開催レポート


