
学会の活動
研究会報告
ここでは、研究事例・交流部会、研究会(学会助成研究)での活動についてご紹介します。
次回開催予定 Next Event
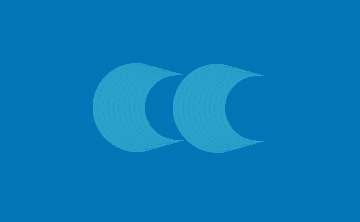
大手小売業の協力で実証実験を予定
2023年4月からスタートした「人的資本経営と効果的IC施策研究会」では
3年目を迎えた今年度には、先進企業の事例研究と並行して、
対話施策の効果を検証する実証実験プログラムを進める方向で
協力企業との具体的な計画を検討しています。
世界各地の政治・社会を覆う分断の構図はニュース画面に映るだけでなく、
わが国企業社会にも深く突き刺さりつつあるかもしれません。
人的資本経営の導入を提言した人材版伊藤レポートの中にも、
対話(ダイアローグ)施策が30か所も登場し、経営推進のドライバーとして位置づけられています。
その意味で今回の実証実験プログラムは、
ある意味伊藤レポート版「実践施策」の可能性を秘めるとともに、
人的資本経営を定着させていく企業文化の要素も孕むのではないかと思われます。
(清水正道・研究会主査)
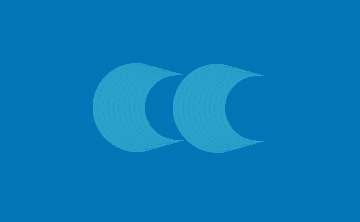
「サステナビリティ広報戦略研究部会」メンバー募集のお知らせ
サステナビリティ経営時代における広報・コミュニケーションの在り方を探求してきた
「サステナビリティ広報戦略研究部会」の第3期(2025~2026年度)メンバーを募集しています。
これまでの第1期(2021~2022年度)、第2期(2023~2024年度)の研究成果を踏まえ、
第3期では、企業が持続可能な社会の実現に貢献しながら、
信頼性の高いサステナビリティ広報戦略をいかに構築するかをテーマに、
国際的な潮流や規範にも目を向けながら検討を深めていきます。
活動は、年6回程度、ハイブリッド(都内+オンライン)またはオンライン形式で開催予定です。
各回には、国内外の企業・団体のサステナビリティ推進部門や広報担当者、国際NGO、
国際規範に詳しい有識者など、さまざまな視点をもつ専門家を招き、
事例研究とディスカッションを行います。第1回の会合は、5月30日(金)19時~、
都内+オンラインのハイブリッド形式で
今後の研究計画など話しあう予定です(登録者には詳細をご案内します)。
部会への参加申し込みはこちらからお願いいたします。
https://www.jsccs.jp/private/Recruitment-of-Member-25.html
※毎回の出席は必須ではありませんので、お気軽にご登録ください。
可能な限りアーカイブ視聴もご用意いたします。
問い合わせは、安部(abeyu@ruri.waseda.jp)までお寄せください。
みなさまのご参加、お待ちしております。
(安部由紀子)
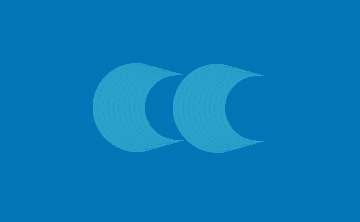
理論研究部会2024:定例会3月報告、4月予告
本部会では毎月海外の広報研究資料を読み、議論をしています。
【報告】【報告】第11回3月15日(土)西川会員が、
ノルウェー政府省庁におけるコミュニケーション専門職を分析したFigenschouらの論文を報告。
論文は、「情報提供者」と「スピンドクター」の2つの理想型を提示し、6つの次元で役割を整理。
実証分析では両者の特徴を併せ持つことが明らかになった。
議論では、日本の行政広報への応用可能性、政治化の程度、
戦略的広報の位置づけ、用語や比較軸の妥当性が論点となった。
【予告】第12回4月19日(土)は普段と違い、
メンバーが互いの研究領域に対する理解を深める機会とする予定。
第一部で各自がこれまでの研究、現在取り組んでいる研究などについて5分程度で紹介し、
第二部で自由にディスカッションをする。
今後の開催日程や過去に扱った論文は以下のスプレッドシートでご覧いただけます。
参加希望者は国枝( t_kunieda@sophia.ac.jp )までご連絡ください。
https://bit.ly/rkbhi
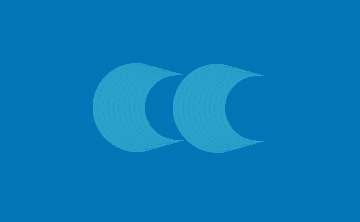
紛争と国際世論とパブリックリレーションズ
「情報流通構造の事例研究会」オンライン開催のお知らせ
テーマ:「紛争と国際世論とパブリックリレーションズ」
近年、戦争や紛争における「情報戦」は、戦場の戦いと同等、
あるいはそれ以上に重要な要素となっています。
SNSやメディアを駆使したPR戦略がどのように国際世論を形成し、
政策決定に影響を与えているのか。
本研究会では、湾岸戦争時の「ナイラの証言」を起点に、ロシア・ウクライナ戦争、
イスラエル・パレスチナ紛争、その他近年の情報戦の事例を交えながら、
PR会社の役割を分析します。
【開催概要】
日時:3月27日(水)17:00~18:00
開催形式:オンライン(Googleカレンダーで招待します)
(事前登録制)
主なトピック
・「ナイラの証言」とPR会社の関与
・ロシア・ウクライナ戦争におけるゼレンスキー大統領の情報戦略
・イスラエル・パレスチナ紛争の情報戦と国際世論
・PR会社の倫理と情報操作の境界線
国際関係・広報・メディアに関心のある方のご参加をお待ちしています!
参加申し込みはこちら:tashiro@materialpr.jp (田代 順)
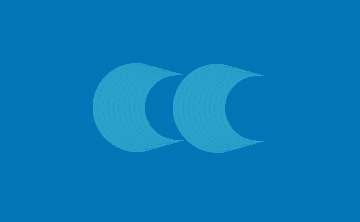
九州部会
九州部会 部会長・小野豊和
1.研究発表全国大会(南山大学)でポスター報告。中部・関西・中四国・九州の
4つの地域部会コーナーを設けていただきました。
2.次回研究会
・日 時:11月28日(木)18:30~20:00
・テーマ:(仮)「漫画ビジネスと漫画家育成」
・講 師:日本漫画塾代表 信濃裕馬社長
*九州部会対象ですがオンライン開催なので参加希望者は
小野(⇒ toyokazuono@gmail.com)まで。 申込〆切:11月20日
(部会長 小野豊和)
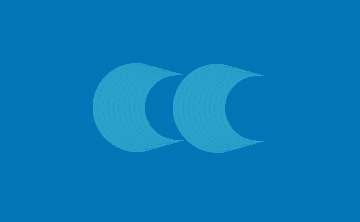
情報流通構造の事例研究会定例活動報告
10月29日情報流通構造の事例研究会定例報告
【小池百合子・石丸伸二・蓮舫の広報戦略に関する概説】
2024年の都知事選において、小池百合子氏、石丸伸二氏、蓮舫氏は、
それぞれ異なる広報戦略を展開し、ターゲット層やメディアの活用方法に違いが見られました。
3人の候補者は、それぞれ異なるメディアとメッセージの組み合わせで選挙を戦いました。
小池氏は既存支持基盤を守るための安定的な戦略、
石丸氏はSNSを駆使して若者層にアピールする攻めの戦略、
蓮舫氏は親しみやすさと既存政党への批判を軸にした戦略を採用しました。
これらの戦略の違いは、選挙結果に直接的な影響を与えたと言えます。
【議論、意見、指摘】
YouTubeを活用した情報流通構造と選挙戦略に関する考察
2024年の都知事選では、YouTubeを中心とした編集動画の拡散が
選挙結果に大きな影響を与えました。
特に、候補者の一部はSNSを積極的に活用し、投票者の関心を引きつけることに成功しましたが、
一部の個人編集者が広告収入を目的として選挙応援を行った側面もあり、
情報流通が商業化される一面が露呈しました。
情報流通構造と商流の一体性
メンバーからの指摘として、情報の流通が「金流」や「物流」と結びつき、
一体化して商流として機能している可能性が示されました。
これは、選挙活動においてもマーケティング的なアプローチが重要視され、
情報が資本や物流と密接に関連している現状を反映しています。
小池百合子氏の選挙妨害とSNS批判
選挙期間中、小池氏には選挙妨害の事例もあり、ネガティブな影響を受けました。
また、今回の選挙では、衆議院選における最高裁判事の信任投票においても、
SNSでの批判が高まり、結果的に約10%が不信任票を投じたことが報告されています。
YouTubeによる拡散の影響
特に石丸氏は、YouTubeを戦略的に活用して若年層を取り込み、支持を拡大しました。
彼の支持者の約半数がYouTubeを参考に投票行動を決定したとされ、
これが選挙戦の新たな形を象徴する結果となりました。
一方で、動画の編集者や拡散者は広告収入の目的も持っており、
選挙応援と商業利益の両立が複雑な状況を生みました。
今後の課題
SNSの利用が今後の選挙においてますます重要になる中で、
情報の透明性と商業化のバランスをどう取るかが課題です。
また、SNS上の批判が投票結果に及ぼす影響についても、さらに分析が必要です。
政治と商業の交差点におけるリスク管理の強化が求められるでしょう。
情報流通の商流との一体性、SNSを通じた批判の影響、
そして今後の選挙戦における課題を概説しました。
以上
次回は11月26日18時からオンライン開催
メンバーからの自主発表がなければ
「#なめくじ投稿から倒産は防げた?」を検証します。スポット聴講も可能です。
主査: tashiro@materialpr.jp
(田代 順)
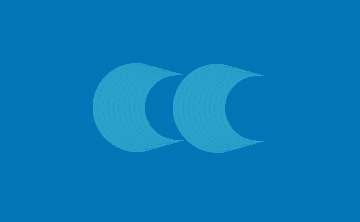
サステナビリティ広報研究会の活動報告
当研究会では、サステナビリティ経営時代の新たな広報機能をどのように現場実装できるのか、
事例研究を重ねています。
本年度は、次の2つの機能に焦点をあてています。
社会課題をわかりやすく説明し、自社のそれに対するスタンスを明示しながら
ステークホルダーに活動への参加を促す「コンテキスト(文脈形成)機能」と、
志をともに協働するパートナーと出会い、増やす「関係性構築機能」です。
これまでに、丸井グループやサイボウズ、UNDP(国連開発計画)、ヤマハ発動機、
アクサホールディングスの事例のほか、
中小企業におけるCSRコミュニケーションの研究報告を聞かせていただきました。
次回11月下旬の研究会では、公益重視型企業としてB Corp認証をうけているファーメンステーションから、
企業と社会の関係づくりの実践の話をうかがう計画です。
これまでに検討した内容を、第30回研究発表全国大会にて口頭発表する予定です。
会場にて議論できることを楽しみにしています。
(研究会主査・坂本文武)
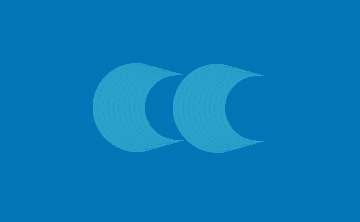
まず「対話」用語の分析作業を開始しました。
HCM交流会/研究会では、5月15日(水)夜、オンラインで第1回交流会を開催したのに引き続き、
6月4日(火)には第1回対話コミュニケション(COM)部会を開催しました。
また6月下旬を目指して効果測定部会を立ち上げることも予定しています。
今年度のHCM研究会は、先進事例のケーススタディを主に学ぶ「交流会」と、
2つの研究テーマの解明を目指す「研究会」で構成されることになりました。
いわば交流とテーマ研究を両立させるハイブリッド型の作業で進めたいと
意図して活動を開始しました。
研究テーマの方も、人的資本経営の取組成果を確認する手法を検討する「効果測定部会」と、
人的資本に関わる経営活動を深掘りして企業文化にまで高めることに不可欠な
対話手法の標準化を目指す「対話COM部会」の2つのテーマを追いかけていくことにしました。
いずれの部会でも、11月開催の研究発表大会(南山大学)までには中間報告を行い、
会員各位からの意見をしっかり伺いつつ、実務に役立てられる手法の提案を行っていく予定です。
ただし効果にせよ対話にせよ、それらは日常用語としても身近なだけに、
安易に使用される嫌いがあります。そのため各々の実際の使用例などから
それらの意味を確認していくことが求められるのではないでしょうか。今後の作業が楽しみです。
(清水正道 HCMIC交流会/研究会・主査)
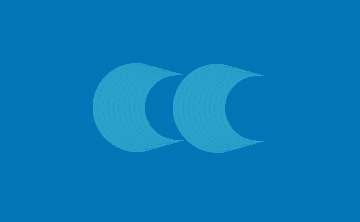
情報流通構造の事例研究会
開催報告
5月27日(月)、広報学会の研究会「情報流通構造の事例研究会」がオンラインで開催され、
「森永製菓の広報戦略研究」がテーマとして取り上げられました。
森永製菓の「バニラモナカジャンボ」が発売50年を迎えるロングセラー商品でありながら、
常に製品改良を行っている点が強調されました。
特に、モナカの吸湿を防ぐ新技術「チョコの壁」を導入し、
食感を維持する取り組みが紹介されました。
広報とマーケティングが緊密に連携し、
製品の訴求ポイントを明確にしたプロモーション活動を展開しています。
2021年から24年までのニュースリリースと掲載記録から
「水面下の広報戦略」を考察しました。
最近では、「パリパリ食感」を研究テーマに据え、横浜国立大学との共同研究を通じて、
その効果を科学的に検証しています。
このような研究テーマは、メディア掲載には必ずしも有利ではないものの、
社内広報的には大変効果的であり、社員のモチベーション向上や企業の信頼性向上に寄与しています。
研究会では、これらの緻密な広報活動についての議論が深まり、
参加者にとって有益な知見が共有されました。
次回は6月29日にオンラインで開催します。
(田代 順)
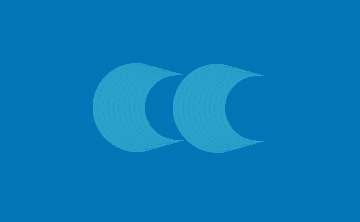
情報流通構造の事例研究会活動報告
1月定例 オンライン開催
テーマ「ビール大手各社の新製品発表の施策を比較検証する」
背景:10月にビール酒税が減税になり、各社が個性的な新製品を投入した。
日経MJでは8月下旬から9月にかけて各社の新製品を流通向け、
量販店向けに各社の動向を詳しくレポートしている。
担当は日本経済新聞東京本社、
報道ユニット食品産業グループ「飲料業界」担当Y記者
激化する新製品ローンチで日経記者の取材チャンスを最大獲得できたメーカーの
水面下の広報施策を読み解く。
戦略的な情報提供、リークや日経記者の単独取材獲得など紙面から読み取りました。
次回開催は2月26日月曜日18時より
オンライン開催の予定
参加希望者は 田代 順 tashiro@materialpr.jp まで
(田代 順)
過去の研究会報告


定例活動報告

九州部会研究会報告

理論研究部会2024:定例会2月報告、3月予告

理論研究部会2024:定例会1月報告、2月予告

企業で「対話トリセツ」実証実験の開始へ

情報流通構造の事例研究会活動報告

九州部会第3回研究会案内&募集

理論研究部会2024:定例会12月報告、1月予告

定例活動報告

広報部門における生成AIの導入率は37.2%


