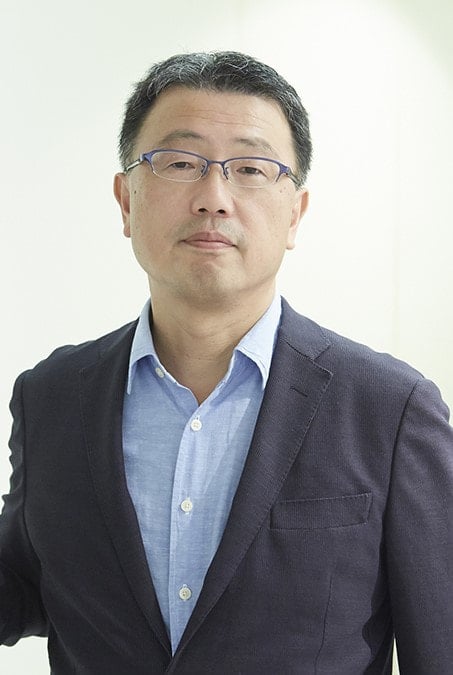日本広報学会について
理事長挨拶
今ほど「広報の重要性」が増している
時代も無いのではないでしょうか。
今日世界は、難題に満ちています。中東を始め多くの地域で紛争が収まらず、国家同士の貿易摩擦の行方もなかなか見えて来ません。日本国内でも、少子高齢化に歯止めはかからず、東京一極集中と地域の苦悩も収まる先が見えません。企業に目を移せば、今までに類を見ないほどの深刻な不祥事が指摘され、企業業績にも多大なマイナスの影響を与えています。個人に返っても、生きづらさを感じる人が増え、人生100年時代の生き方、言ってみれば“個人としての経営戦略”を探し求めている人も数多く出現しています。
そんな難題だらけの世界では、直線的な施策だけでの解決はおぼつかず、結果として、広報の重要性が今まで以上に増して行く。私自身は、そう実感しています。
日本広報学会では、2023年6月20日に、多くの会員の皆様の大いなる奮闘努力の末に、新たな「広報の定義」を策定しました。多様な組織や個人が、この定義にあるような“広報”を今まで以上に活用して、難題の数々を少しでも良い方向に持って行くことを期待していますし、実際に広報にはそうした機能が内在していると、個人的には信じています。
日本広報学会は、企業・行政・団体から非営利組織までの多様な組織と、さらには個人の広報・コミュニケーション活動を研究の対象としています。この分野の理論と実践の両面から研究・情報発信、さらには会員に対する啓発活動など、さまざまな活動を行い発展してきています。
広報・コミュニケーションの領域は、研究の面からも、マネジメント実践の面からも、総合的かつ学際的です。関係する学問領域も経営学、マーケティング論、広告論、組織論、情報行動論、言語・メディア・ジャーナリズム、さらには国際地域研究などと広範囲です。組織経営の面でも、トップマネジメント、 広報・IR部門、マーケティング部門、人事・総務部門、情報システム・ナレッジ部門など多くが関係し、それだけに、多面的なアプローチが求められる領域です。
当学会は、こうした領域の多様性から、幅広い専門、職種からの会員で成り立っていることが特色です。関連する研究を行う大学などの研究者、所属する組織の広報・コミュニケーション活動を実践する方、あるいは関連サービスを提供するPR会社やメディア関連事業者の方など、多様なバックグラウンドを持った会員からなり、数百人の個人会員に加え、数十社の法人が法人会員として活動しています。このことが、実務者と研究者の幅広い情報交換と議論を可能にしています。
日本広報学会では、広報・コミュニケーション分野の理論・実践の両面からの発展に向け、先進事例の分析や交流、仮説や理論の提示などの研究・教育活動を展開しています。また今後は、研究および学会活動のさらなる国際化にも取り組んで行きたいと考えています。企業・行政、諸団体、NPO/NGOなど、あるいは大学や研究機関で、広報・コミュニケーション活動に携わり研究している皆さまの、幅広い参画を、ぜひお待ちしています。
佐藤 達郎
日本広報学会 理事長
(多摩美術大学教授 / 学長補佐)